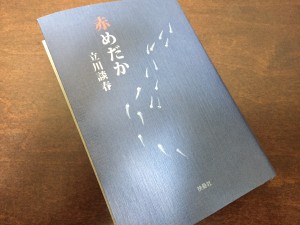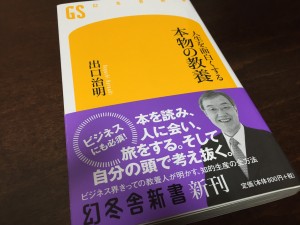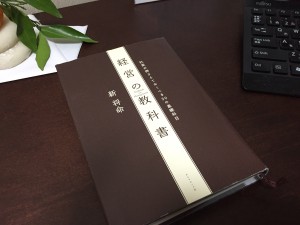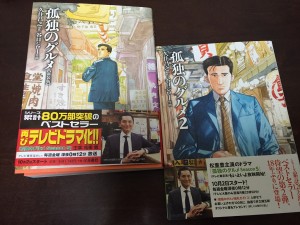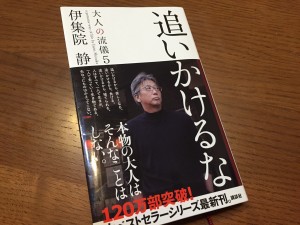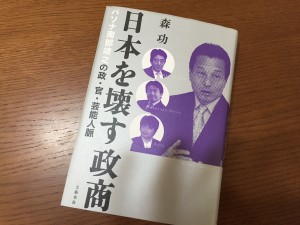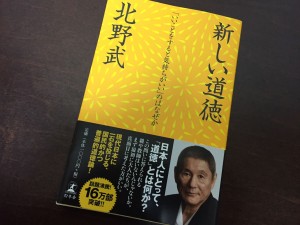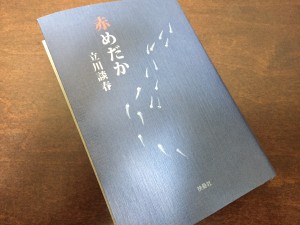
単行本が出版された時に読もうと思っていたが、
しばらくするうちにその存在をすっかり忘れていた。
昨年末にTVドラマ化され、その存在を思い出した。
ドラマはあえて見なかった。
見てしまうと何となく書籍の良さが感じられなくなってしまうと思ったから・・・。
初めて知ったが、著者の立川談春氏は僕と同い年。
ドラマ「ルーズヴェルト・ゲーム」「下町ロケット」でその姿を見たのが初めて。
(人相の悪いイツワ電器の社長役も人間味あふれる経理部長役も最高だった。)
落語は当然聞いたことはない。
てっきり年上と思っていたが、同級生なんだ。
50代半ばに見えてしまうのは僕だけだろうか。
すみません・・・。
お会いしたら、「オレのほうが断然若い」と言われそうだけど(笑)。
ジャンルとしてはエッセイになるようだが、自伝小説に近い。
読み進めるうちに何故か懐かしさを感じた。
昔、この手の書籍をよく読んでいた感覚が蘇ってきたのだ。
誰だろうか?
椎名誠?嵐山光三郎?
破天荒な若さがいいじゃないか。
お金のない下宿生活を同じような貧乏仲間と一緒に青春している。
そんな感じ。
それはそれで大いに共感できるし、今からすればその時代の関係性に憧れも抱く。
何をしても許される時代。とても今では考えられない。
そして大人になっていく。
経験や年齢と共にボクからオレに変化していくさまもいい。
やはりビジネス書ばかり読んでいると感性は鈍る。
人として大切なものを失くしてしまうような気もする。
自分の感性が豊かだとは全然思わないが、
少なくとも肌感覚の感受性は持ち合わせていたい。
(そんな表現はないと思うけど・・・笑)
機会があれば、真打の落語も聞いてみたい。
東京で真面目な講演や勉強会もいいが、
たまには浅草あたりでそんな場を持つことも十分仕事と言えるだろう。
よしっ、それを理由に出張の計画を立てるかな・・・。

僕の映評ブログを読んだ映画配給会社から試写会をご招待いただいた。
どうやら僕が映画を評論することで興行収入は大きく変わるらしい。
評価すべきブログを期待されているようだ。
そんな偉大な力がこのブログにはあるんだ・・・。
な~んて、ウソです。スイマセン。
って、最初から分かってる?スイマセン・・・。
しかし、公開前の試写で鑑賞したのは本当の話。
多少の宣伝も含め、感想を書くことにしたい。
本作品はスティーブ・ジョブズに関心がなければ観るべきではない。
また、半生を一定レベル知っていないと映画についていけない。
何より演出の手法は斬新で切り口は面白いし、人間の描き方も秀逸。
スティーブ・ジョブズを演じたマイケル・ファスベンダー氏の役作りと年の取り方は感動もの。
それだけでも観る価値はある。
しかし、ジョブズを知っているのが前提。
より映画を楽しみたいのであれば、英語の理解力が高い方がいい。
とにかくセリフが多く、ずっと喋っている。
英語がサッパリな僕は字幕を読むのが忙しく、映画の展開についていくのがやっと。
日本語訳ももしかしたらニュアンスは違うかもしれないので、
英語をしっかりと聞き取れる能力があると一層面白くなるはずだ。
これまでは一本の映画の感想。
そして、もう一つは経営者目線でのスティーブ・ジョブズ像。
ここで描かれていることが真実かどうかはわからない。
映画「ソーシャル・ネットワーク」を観たザックバーグ氏が
「オレはこんなんじゃない」と文句を言ったとか言わないとかあるが、
もし、ジョブズ氏がこの映画を観たらどう思うのだろう。
「これは凄い!その通りだ!」と絶賛するのか、
「バカにするな!」と怒り狂うかは分からない。
しかし、凡人からすれば、その人間性は異常と感じるはず。
逆にそんな人間性だからこそ、類まれな才能を有し、
世の中にないサービスを提供することもできるのだろう。
僕がどんなにグデグデに酔っ払い人格が変わったとしても
あんな行動を取ることはできない。
プレゼン前にあんな事態に追い込まれたら、
本番はしどろもどろになってしまう。
それがある意味、能力の違いでもあるし、天才と変態の紙一重の差ともいえる。
憧れは抱くが、あんなふうにはなりたくはない(笑)。
いろんな意味で勉強になる映画。
Appleファンはぜひ、ご覧いただきたい。

自然に涙が流れてきた。
そんな劇的なシーンではない。
ただお互い見つめ合っているだけのシーン。
なぜかその場面で涙が流れてしまった。
この長い映画の象徴するシーンと勝手に体が反応してしまったのだと思う。
まだまだ僕の感性は鈍っていないようだ(笑)。
こんなことを書いても映画を観ていない方はさっぱりわからないだろう。
しかし、詳細は何も語らないほうがいい。
とにかく観てもらえばそれでいい。
友人がスティーヴン・スピルバーグとトム・ハンクスのコンビは名作揃い
といっていたが、本当なんだ・・・。
だから、もうブログに書くことがなくなってしまった。
どうしよう、困ったな・・・。
あと何を書けばいいだろうか(汗)。
本作品は実話を基にしている。
アメリカとソ連の冷戦期を描いているわけだが、
こんな事実を知っている日本人はどれだけいるんだろうか。
単純な僕の知識不足ではあるが、ひとりの民間人に国の重要な任務を任せてしまう
大国の傲慢さ(叱られるかな?)におののいてしまった。
また、社会主義の国を同一に見てしまう自分も愚か。
ソ連と東ドイツの歴史上の関係性ももっと知っていてもよさそうだ。
未来を描く映画もいいけど、歴史を学べる映画も自分にとっては価値がある。
先月観た「杉原千畝 スギハラチウネ」もそうだし・・・。
世界史で学んだことしか知らないのでは片手落ち。
かといって、なかなか学ぶ時間までないし。言い訳だけど。
トムハンクス演じるドノヴァン弁護士のような人物ばかりであれば戦争なんて起こりようもないし、
国同士のエゴも抑えられるだろう。
だが、現実は不可能だし、僕がいくら偉い人になったとしてもこんなふうには絶対になれない。
(当然です・・・)
映画を通して感じたこととして、主人公を取り巻く大衆はやはり自分勝手。
それは今も昔も変わらない。
ソ連のスパイを弁護すればどんな理由であろうと叩き、
米軍の乗組員を救出すれば称賛する。
主人公の行動はぶれることなくどんな場所でも同じだ。
その本質を見られることは少ない。
結局、今の社会でも同じで僕たちはその中で生きている。
自分自身にとってに何が正しいのか見極める力が必要。
言えるのは、いつも真実が感動を与えてくれる。
それは忘れてはならない。
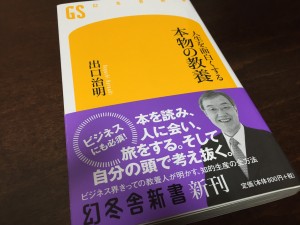
著者の出口さんとは過去2回お会いし、話をさせていただいた。
1回目は約2年前の「中部経営塾」。
この時もブログに書かせてもらったが、人としての器の大きさとサービス精神には感動した。
リーダーシップの在り方も・・・。
僕の後継者の選び方の質問にも明快な回答を頂けた。
もう1回はその3ヵ月後に行われた世界史の勉強会。
その造詣の深さにも感動を覚えた。
この時のブログでも自分の知識不足を嘆いていた。
あれから1年半以上、経過し、
自分の知識不足は少しは解消したかと思いきや、全く変わらない。
本書の読んで、自分の学のなさに改めて愕然とした。
過去のブログを読み直し、自分の成長のなさに改めて辟易した。
本書の帯には
「本を読み、人に会い、旅をする。そして、自分の頭で考え抜く。」
と書かれている。
何も特別なことではない。頭では理解していること。
しかし、その文言をそのまま行動に変えられている姿を見るとひるんでしまう。
決して簡単なことではないのだ。
本を読んでいるつもりでも、人に会っているつもりでも、
教養に落とし込むまでには至っていない。
その場の満足感に浸りきっている。
それが悪いことではないだろうが、出口氏に言わせれば
「キミは何をチンタラやっているのだ!」と叱られそうだ。
「数字・ファクト・ロジック」で語ることと
イデオロギーや感情論の「国語」で語ることは大いに異なる。
それが誰に対して、どう議論するのかでも教養を問われる。
価値観が一致するとか、共感するだけでは成立しないことは多いはず。
まだまだ僕自身の経験値が足りないのも間違いないし・・・。
旅行もただポカ~ンと口を開けて、のんびりしているだけでは意味がないのだろう。
そこでも歴史を学び、町を知ることが求められる。
どうやらやることはいっぱいだし、49歳でも50歳でも関係ないようだ。
いまのままでは物足りなさすぎ。
もっともっと教養を積む努力をせねば・・・。
反省は続く・・・。うむ。
この休暇中、新将命氏の「経営の教科書」を改めて読んだ。
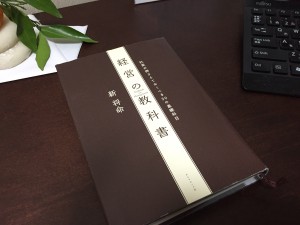
初めて読んだのが約6年前。トップを任されて間もない頃だった。
その当時、始めたばかりのブログにも書いたのだが、今読み返してみると感じ方がかなり異なる。
曲がりなりにも6年間、会社を任されてきて自分なりに学んできたことも多かったのだと思う。
当時はどちらかと言えば気づきばかりだったが、今回は共感に変わっている点が数多く見られたからだ。
数多く見られたからといって、実行できているとは限らない。
できている点もあればそうでない点もある。
むしろまだまだ足りないのが実態。
だからこそ、改めて読んで学ぶ必要がある。
やはりここに書かれているのは原理原則。
リーマンショック後の厳しい環境下の書籍であっても本質は変わらない。
今読んでも色褪せることはないし、再度意識しなければならない点、
すっかり抜け落ちている点、多少なりとも及第点を与えられている点が再認識できた。
新氏は特別難しいことを語っているわけではない。
すべて自分で編み出したノウハウや考えではない。
松下幸之助氏やドラッカー氏の引用も多い。
経営の原理原則をすべて自分自身の考えで持って、書き上げることは難しい。
多くの方からいい影響を受け、それを実践するうちに自分のスタイルに落とし込んでいるに過ぎない。
新氏もその一人で、常に学ぶ姿勢を持ち続けているということ。
最初に読んだ時はそこまで感じなかったが、その積み重ねが一流の経営者として証明されている。
自分に驕ることのない人間性を含め、時代の変化を読みながら形作ってきた結果だと思う。
だとすれば、僕のような低いレベルは一年に1回くらいは読み返す必要がある。
事業の倫理観、自分のあるべき姿、社員への仕事の任せ方、
ロジックと感情の関係性など、改めて重要性を感じさせてもらった。
出来ている面はさらに活かし、出来ていない面は修正していく。
シンプルだけどそれを繰り返しをしていけば、会社は上手く機能するはず。
凡事徹底、当たり前のことを継続すれば、会社を存続させるのはそんなに難しいことではない。
社会に対しての目的をはっきりさせればいいこと。
大切なのは原理原則。
そこはどんなに調子がよかろうが忘れてはならない。
そんな意識を持つ一年にしていきたい。
会社帰りに名古屋駅のジュンク堂書店に立ち寄った。
大型店にしかないだろうという書籍を探すためにお邪魔したのだが、
目的の書籍の在庫は残念ながらなかった。
「さて、どうするかな・・・」
と各売り場を眺めていると目に飛び込んできたのがこの書籍。
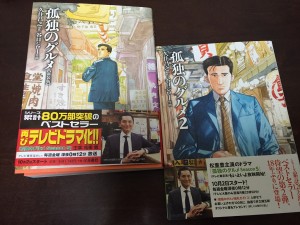
衝動的に購入してしまった。
マンガを買うなんて何時以来だろう。思い出せないくらい昔のこと。
「TVも終わってしまったし、食べ物ブログの参考書にでもするか。」
と前向きな解釈をして、早速、読むことにした。
「井之頭氏の印象はTVとはずいぶん違うなあ~。」というのが読み終えた感想。
原作には昔付き合っていた彼女も登場するし、お店で店主やお客さんとケンカもする。
このケンカは全うな理由で井之頭氏の肩を持ちたくなる。正義だ。
そして、圧倒的な強さ。こんな人物像なんだ・・・。
食べ物ブログの師匠がブログネタで、「孤独のグルメ」のアプリとやらを使いイラストが登場する。
そこには「はふ、はふ、うおォン、俺はまるで人間火力発電所だ。」
というセリフが出てくる。
あっ、そうそう。
先日、師匠と飲んだ時にこの表現に対して叱責を受けた。
「キミのブログはうおん、うおんとなっている。
正式にはうおォンだ。まるでダメじゃないか!」
確かに原作も”うおォン”という表現。
師匠、すいませんでした・・・。
話は逸れたが、人間火力発電所って、
いろんなシーンで使われているのかと思っていたが、2巻の中で一か所しか出てこない。
焼肉屋さんでの食事の場面だけだ。
なんだか師匠のブログに騙された感じで、僕のブログにも何度となく使ってしまったことは大いに反省。
これからはその表現を控えるようにしたい(笑)。
「いいぞ、いいぞ~」とか、「なんだか凄いことになっちゃったぞ。」
はあちこちに登場するので、安心して引用できそうだ。
TVシリーズはseason5しか見ていないので、
何とも言えないが原作に出てくるお店はTVには全く出ないのではないか。
そもそも原作の世界は実在するお店なのか架空のお店なのか、わからない。
すべてが美味しいお店ではなかったりするし・・・。
何も考えずに単純に楽しめばいい。
リビングで読んでいたら、息子が手に取って言った。
「マンガで920円、高っ。こんなの読んで何の意味があるの?」
「いや、それは・・・」
答えることができなかった。
何の意味があるのか。
誰か教えてほしい・・・。
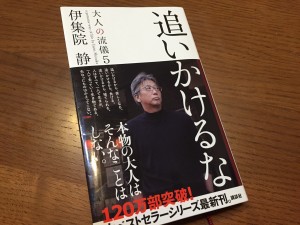
このシリーズを読んでいると人として大切なことを思いださせてくれる。
僕の毎日は会社が中心に回っていて、何よりも最優先である。
それは間違っていないし、そうすべきだと思っている。
しかし、そんな毎日を過ごしていると肝心なものを失くしていくような気もしている。
決して儲けることばかり考えているわけではないが、
どうすれば会社は成長するのか、人を育てるには何をすべきか、
どんな戦略がこれからは必要になってくるのか、そんな事ばかり考えている。
それは常に何かを追いかけている状態ともいえるだろう。
本書の帯にも
”追いかけるから、苦しくなる。
追いかけるから、負ける。
追いかけるから、捨てられる。
人はすべて、一人で生まれ、一人で去っていく生き物である。
失ったものは帰ってこない。”
当たり前のことだが、言われないと忘れ去り、気づかないまま過ごす毎日となってしまう。
資本の論理からかけ外れ、自由気ままに生きているように見える著者だが、
生きる上での責任は常に持ち合わせ、周りに向き合っている。
視点もはるかに高い。
ビジネス以外の大切なものを教えてもらっているような感覚。
だからこそ体が欲して、このシリーズに手が伸びてしまうのだろう。
本書の中に
“便利なものには毒がある。手間がかかるものには良薬が隠されている。”
という一文がある。
何かと便利な生活を求める身に対してのまっとうな考えだ。
肝にも銘じなければならない。
著者とお酒を酌み交わす機会はないだろうが、
(当たり前です。あると嬉しいけど・・・)
もし、そんなシーンがあったりするときっと言われるだろう。
「男が美味いとか、なかなかやるじゃないかとか、言うんじゃない。おまえはバカか!」
ありがたく説教も受けてみたい。
「あれは役割でやっているだけなんです・・・。」
「おまえはバカか、男は言い訳しないものだ。」
と一蹴されるだろうけど・・・。
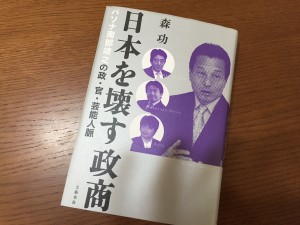
日経新聞の書籍広告を見て、ミーハー的に購入してしまった。
書籍の帯には
”安倍総理の政策ブレーンにして、ASKAと愛人が出会った秘密パーティの主催者・・・。”
とやや過激に書かれている。
実際にパソナの南部さんには一度もお会いしたことなければ、雲の上の存在でしかない。
パソナグループの社長との面識はあっても、そのグループと代表とは別次元の話。
本書に書かれていることがすべて真実かどうかはわからない。
確かに国の助成金をことごとく入札で落とし、ごっそり持っていく手腕はここに描かれている背景がある
と想像できるが、まるでドラマのような世界は本当に実現するのだろうか。
それは半径10km以内で世の中を見ている僕の視野の狭さを物語っているだけかもしれないが、
実際、全く他人事の世界でしかない。
著者は南部氏をどちらかと言えば否定的に書いているが、トップ企業の座を確保しようとすれば、
少なからずこのような政治的な才能が求められるのであろう。
その時点で僕の描ける事業領域は決まってしまっているのかも・・・。
う~ん、それは仕方のないことですね、残念だけど(苦笑)。
しかし、一方でこの手の書籍を読むことで、事業を推進していくためには経営手腕だけでなく、
別の能力を求められる必要があるとも感じる。
それはここに書かれているように秘密の場所でパーティーを繰り返すとか、
落選した議員を囲って恩義を売るということではない。
人とのネットワークを大切にするにしても、もっと打算的な付き合い方をしなければならない。
お金の使い方をしなければならないということ。
その点でいえば僕は全くの未熟者で、もっと計算高くならなければならない。
実現可能性が高いかはともかく、もっといろんな橋を渡れという話ですね。
円頓寺あたりに秘密のパーティールームでも作ってみるかな。
冗談はともかく、政・官・民の間にはそんなことがうごめき合っているみたいだ。
誰しも表の顔と裏の顔を持っているのかもしれない。
自分がその存在になれないとしても、それで世の中が成り立っていることの現実を理解し、
その中で戦えるだけの人間力を養うことは必要ありそうだ。
いい意味でも悪い意味でも参考になった一冊。
勉強させてもらいました。

杉原千畝氏の存在を少なくとも30歳くらいまでは知らなかった。
それは知識不足もあるだろうが、
僕が日本史を学んでいた時代には登場したことはなかったはずだ。
見方を変えれば、ルールを破り自分勝手な行動をした官僚。
認められるべき存在ではないだろう。
きっと海外からの称賛の声にやむを得ず、
その実績を称えた面もあるのではないだろうか。
もう周知のことかもしれなけど・・・。
本来であれば、もっと早い段階で映画化されてもよさそうなものだが、
そんな理由もあるのかと素人ながら思ってしまう。
僕が映画を観た理由も単純。
あえて国の方針に異を唱え、
自らの考えを通した方の生き様はどんなもんだろうという興味。
その時代の日本の置かれた状況を確認する意味もあるが、それほど深い理由はなかった。
観た感想はなるほど~というもの。
観ておくべき映画だとは思う。
150分という長さは妥当だが、
すべてを描き切れたかと言えばそうではないようにも思える。
もう少し人物像を落とし込んでいけると、
よりその想いがこちらにも伝わったのではないだろうか。
そのあたりはもったいない。
せっかくなら日本人監督にこの映画を撮ってもらいたかった。
日本と関わりの深いチェリン・グラック監督の方が
客観的な視点を持ち合わせているかもしれないが・・・。
流れる音楽はどうも聞き覚えがあるように感じた。
ドラマ「ハゲタカ」の音楽に似ていたのだ。エンドロールで理由が明らかになった。
共に佐藤直紀氏が担当されている。近い音楽になることは当然こと。
これもよかった。久々に「ハゲタカ」が観たくなった。
そして、奥さん役の小雪。
役作りなのか、子供を産んだせいなのか、
以前より、ちょっとふっくらしたような・・・。
余計なお世話ですね(笑)。
まだまだ日本映画には題材にすべき実話は多い。
映画を通して、もっと勉強したいものだ。
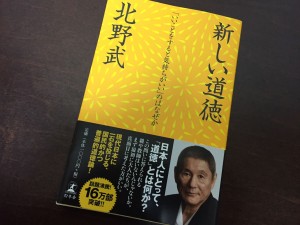
もしかしたら物事の本質をついているのかもしれない。
普段、何げなく生活し良し悪しを考えずに過ごすことも多い。
それはいい事、悪い事を考えないのではなく、
これまでの常識に沿った行動をしているだけで、自分なりの正解は持っている。
それは過去から植えつけられた価値観でもあるかもしれない。
自分自身でも自分の中にある価値観が古いと感じたり、他人と異なると思うことは、しばしば。
今のところ、それを押し付けるような行為はしないし、否定するような発言もしない。
厳密にいえば、酔っぱらって議論する時は引っ張られている気はする。
それで何度かケンカしたのも事実だし・・・。
やっぱ、ありますね(苦笑)。
そこも含めて道徳と言えるのかもしれない。
本書を読んで改めて思ったのは、「道徳」と「良心」はどう違うか、
「道徳」と「倫理」はどう違うかということ。
「良心」や「倫理」は道徳に当てはまるかもしれないが逆はどうだろうか。
道徳には個人差はないように思われるが、良心や倫理は個人に委ねることは大きいように思う。
だとしたら、どちらを大切にしていけばいいのだろうか。
日常ではそんなことを考える機会はまるでないが、本書のおかげでそれを意識することができた。
やはり北野武氏は天才なのか。
デジタルやインターネットに対する考え方には奥の深さを感じた。
ネットは個人を自由にするものではなく、国全体や地球規模で管理されること、
ネットで手軽に知識を得てもそれは手軽な知識でしかないということ。
ウィキペディアで簡単に調べるが、すぐに忘れてしまう僕自身もそう。
深さがない。反省である。
結局は自分自身の考え、自分自身で正しい答えを出していかないと
最後の最後に自己を確立することはできない。
本書でそんなことを教えてもらったような気がした。