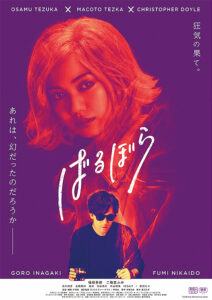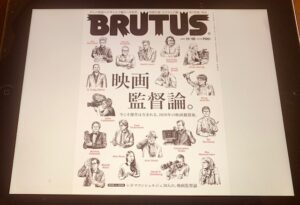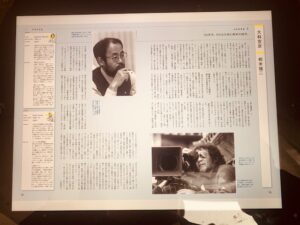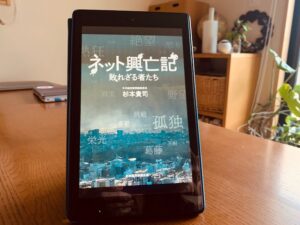12月に相応しい心温まる作品。
なんで12月に相応しいの?と思われるかもしれないが、
大体クリスマスシーズンにはハートウォーミングが多いのが業界の習わし。
ほんとかどうかは定かではないが、そんな気がする。
それに合わせたかのような映画タイトル。
原題「The kindness of strangers」を訳しても、このタイトルとは程遠い。
似ても似つかない。
まるで「愛と青春の旅立ち」のようだ。
まあ、それは許そう。
あながち映画の中身がそれに沿っているから・・・。
ニューヨークが舞台でロシア料理レストランを中心に繰り広げられるし。
そう思うと安易なタイトルか、やっぱり(笑)。
僕は正統派アメリカ映画と思っていたが、それも違う。
デンマーク・カナダ・スウェーデン・ドイツ・フランスの合作。
アメリカもロシアも一切関係なし。
どうしたらこんな合作が生まれるか映画を観ても皆目見当はつかない。
ロネ・シェルフィグ監督がデンマーク出身なのでその繋がりくらいしか理解できない。
勝手な想像に過ぎないし、多分、その想像は間違っていると思うが、
この映画に描かれる世界は万国共通の深いテーマとも受け取れる。
DV、犯罪、リストラ、不倫などそれぞれの事情を抱えた人たちがもがきながらも支えあう。
それも偽善でもなく打算でもなく純粋な気持ちで・・・。
こんな映画を観ると殺伐としたニューヨークの景色も違った色に見える。
それは悪くない。
支えあう人がお互いに立派かといえば、それも嘘。
どこか間違っているし病んでいる。
それでも前を向く気持ちに心を奪われ映画に感情移入していく。
そのあたりも12月らしさといえるのか・・・。
最近の外国映画の俳優はとんと分からなくなっているが、本作もそう。
誰一人として知らない。
その中で僕が惹かれたのは唯一まともな人物ともいえるアリス役のアンドレア・ライズボロー。
ショートカットで颯爽と働く姿は美しく、少し影を感じさせるのもいい。
他にどんな作品があるかググってみたが、惹かれる画像は出てこない。
正直、ろくな画像がない。
そう思うのは僕だけ?
とどうでもいいことを感じてしまった。
単純なハッピーエンドも悪くないが、こんな感じで終わるハッピーエンドも救われる。
結局、人は人でしか救えない。
それはお互いの関係性が希薄であっても、人間同士だから繋がれる。
幸せな気分になれる映画を年末に観れるのはありがたい。