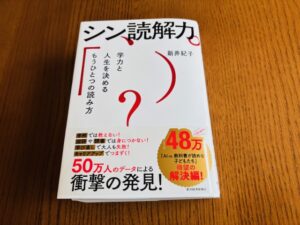2018年に「AIvs.教科書が読めない子どもたち」を読んだ時、かなり衝撃を受けた。
当時、保護者向けの講演の機会が多く、ネタとしても活用させてもらった。
AIにできることと人間にしかできないことの違いが明確だったので、
そのあたりのことを話させてもらった。
そこから7年が経過。
当時、AIにできなかったことが簡単にできるようになった。
ChatGPTが登場してからは飛躍的にその分野が伸びた。
新鮮だったネタもあっというまに古くなった。
僕自身も当時のことは忘れていた。
そんな時に知ったのが本書。
著者の新井紀子さんの研究分野も進んだ。
一貫しているのは教科書を読めるようになること。
タイトルにもある読解力を身に付けること。
前著でもAIをクローズアップしていたが、読解力の必要性がテーマだった。
「岡山と広島に行く」と「岡田と広島に行く」の違いをAIが認識するには一定の時間が必要。
AIには読解力が不足している内容が書かれていた。
しかし、今はそんなものは簡単にクリア。
すべてAIに任せてしまえる時代になったという。
そんな時に重要になるのが「シン読解力」。
若いヤツには必要で自分は関係ないと思っていた。
しかし、本書で出題される問題を解いてみたが、結構間違いも多かった。
おいおい、お前の読解力が不足しているじゃないか(汗)。
冷静に文章を読み論理的に考えれば正解に繋がるが、
軽く読みながら回答すると誤るケースもあったり。
ちょっとマズいぞ・・・と反省。
文章力がないのは百も承知だが、ブログを継続的に書くことで読み手も意識している。
伝える力を身に付けているはず。
逆説的にいえば読解力もあるはず。
ところが・・・。
気をつけなければならない。
その重要性を改めて認識。
最近の若い連中は文章を読まないと思われがちだがそうではない。
昔に比べれば圧倒的に増えているという。
やりとりはほぼメール。
SNSも文字情報は多い。
そうなれば読解力は高いと思われるが、そうではない。
読解力をつけるトレーニングが必要。
新井氏が中心となり推奨するRST(リーディングスキルテスト)がそれ。
HPには
「RSTとは教科書や辞書、新聞などで使われる「知識や情報を伝達する目的で書かれた自己完結的な文書」を読み解く力を測定・診断するツールです。読解プロセスごとに6つのタイプから構成されており、それぞれのタイプで読解の能力値を診断し、学習アドバイスを提供します。」
と書かれている。
鍛えることで数学など直接結びつかないと思われる科目の成績もあがる。
これは大人にも有効。
新聞が読めない大人も多いというし。
僕も怪しかったりして・・・。
本書には「大人のためのトレーニング」という例題もあるので、
試しにやってみるのもいいかもね。