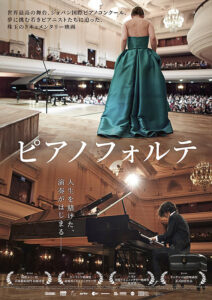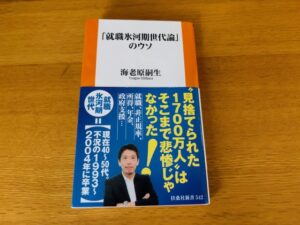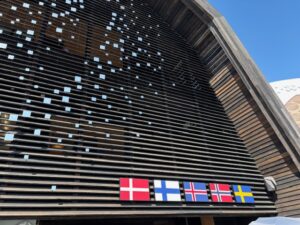事前情報はほぼなし。
162分の上映時間に迷いもあったが何気に評価が高かったので観ることにした。
解説を読むと元革命家のレオナルド・ディカプリオの娘を
軍人のショーン・ペンが執拗に追いかけるというストーリー。
勝手にディカプリオが悪者、ショーン・ペンが正義と決めつけたが、まるで違った。
しっかりと解説を読んだ方がいいか、もしくは事前情報は全くないほうがいい。
設定はディカプリオが主役だが、影の主役はショーン・ペン。
まだまだ元気な60代。
ショーン・ペン演じる軍人ロックジョーがかなりヤバい。
この年齢で筋肉ムキムキな体にも驚かされるが、行動はまともじゃない。
はっきりと変人といったほうがいい。
最大限に権力を活かし憑りつかれたような動き。
確かに最初に登場した時からヤバかった。
こんな書き方をするとホラー映画と勘違いしてしまう。
ネタバレしない程度に解説しよう。
カリスマ革命家女性と結婚したディカプリオ演じるロブ。
2人に間に生まれた娘ウィラ。
革命犯が犯した事件を追う軍人ロックジョー。
あくまでもこれは伏線。
舞台は15年後の現在。
元革命家のボブはすっかりぐうたらで娘の成長だけが生きがい。
そこにロックジョーがある理由から再び現れる。
ごくごく私的でありながら生命線ともいえる理由。
冷静にみればあり得ない展開だが、巻き込まれた側は命懸け。
ロブは酒づけクスリづけで以前のような体力もなく大事なことも覚えていない。
一方、ムキムキのロックジョーは動きも軽快。
誰がみても力の差は歴然。
そんな中で追う、追われる展開。
といってもトム・クルーズのような派手なアクションはない。
スーパーマンのような大義もない。
登場人物はすべて曲者でまともな人は誰も出てこない。
唯一、娘ウィラくらいだがダメ親父に影響を受けている面もあったり。
そこに怪しい組織が絡んできて・・・。
ヒシヒシと迫りくる緊張感がよかった。
ラストもなるほどと唸ってしまったり。
個人的に良かったのが娘ウィラを演じたチェイス・インフィニティ。
意志の強さが伝わってきた。
そして何といってもショーン・ペン。
久々に映画で観たが、こんなふうになっているとは。
これだけキャリアを積んでも更に広げていくのかな。
そんな作品でもあった。
※ブログを書いた後にHPを確認したら、
作品の紹介は「ヤバい以外でお願いします」と書いてあった。
ヤバっ・・・。