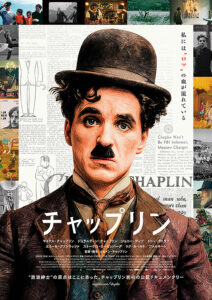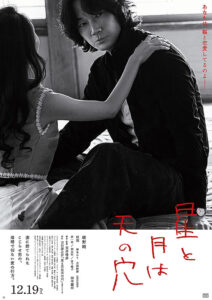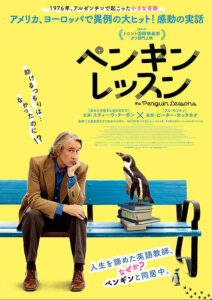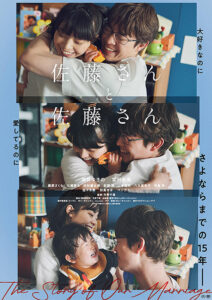公開時はスルーしようと思っていた。
TVドラマは一切見ていないし、ドラマのヒットに便乗する作品に興味を示さなかった。
ところが映画評論仲間と映画コラムニスト見習いが絶賛。
急きょ予定を変更し年末に鑑賞。
12月30日の映画ベストテンブログでは映画館で105本鑑賞と書いたが、結果的に106本。
人の評価は素直に聞くべきだね。
これも知らなかったが、当初は2023年公開予定。
内閣総理大臣役の俳優のスキャンダルにより公開延期になったが、
僕は最初から総理大臣役は石丸幹二でも良かったと思う。
ドラマ半沢直樹もそうだが、ちょっと裏のある役の演技は絶妙。
歌舞伎役者からミュージカル俳優にいいタイミングでの変更じゃないか。
2人の仲間が勧めるように十分楽しめた作品。
但し、期待値を高くしすぎたのは正直なところ。
もう一ひねりあるのかと思ってしまった。
観た人誰しもがいわれるようにドラマを未鑑賞でも理解できる点は上手い演出。
映画を観てからドラマをネットで観る人も増えるだろう。
もしかしたら僕もそうかも・・・。
簡単に解説すれば、厄介な事件のために集められた取調べ専門チーム「緊急事案対応取調班」が、
被疑者である内閣総理大臣を事情聴取し追い込んでいく物語。
専門チームは天海祐希はじめ一癖も二癖もある俳優連中が演じる。
エッジの立つ俳優を際立たせることでドラマの魅力を押し上げている。
足掛け10年とはいえTVドラマでこれだけ豪華な俳優を使うのもそうそうない。
そう考えるとシリーズ全体を見ることで人間関係やヒエラルキーを理解でき、より楽しめる。
特に脇役の大倉孝二や勝村政信あたりは肝心な役だが、映画の尺では深くは描けない。
そのあたりの違いはあるだろうね。
ドラマを観ていない僕が勉強になったのは取調室の可視化。
自白強要や暴力を行わないために取調室は見える化されているか。
活用方法のテクニックもあるが、実際の取調べもあんなふうなのか。
「爆弾」とは大きく異なるのは緊急取調室だからか。
ドラマを見れば分かることかもしれない。
今年もTVドラマの映画化は公開されるだろうが、
勝手にスルーを決めず、人の意見を聞きながら決めた方がいい。
貴重な評価を聞かせて頂きありがとうございました。
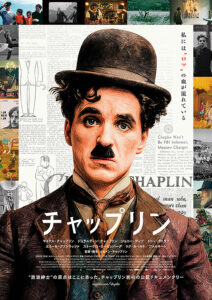
タイトルとポスターからはチャーリー・チャップリンを描いたドキュメンタリーを想像させる。
間違いではない。
しかし、僕が考えるタイトルは「チャップリン家」。
家族を描くドキュメンタリー作品。
レビューをチェックするとさほど評価されていない。
確かにそうだろう。
正直、感動を呼ぶわけでもワクワクさせるわけでもない。
僕はそれでいいと思う。
家族の実情を描くのに面白いもつまらないもない。
お互いの葛藤や確執、のちに生まれる尊敬が綴られるだけ。
目線はチャーリー・チャップリンの息子マイケルが中心。
世界を代表する映画スターを父親を持つ息子の立場を考えれば心情は理解できる。
偉大な創業者を持つ後継者も同様。
後継者育成は簡単ではない。
道を間違える例は山ほどある。
映画界も同じ。
同様の期待をされても当の本人は反発したくなる。
マイケルは自戒を込めながらチャーリー・チャップリンのルーツを探る。
よく登場する言葉はロマ。
ロマとは約1000年前にインドからヨーロッパへ移動してきた少数民族のことで、
かつては「ジプシー」と呼ばれていた。
僕は本作で初めて知った。
チャップリンはロマの血を引き、それが作品にも反映されているという。
ルーツがどんな影響を与えているかは当事者もしく接する者しか分からない。
原動力であり苦しさでもあったのだろう。
それを理解できただけでも観た価値はあった。
マイケルを中心に家族のインタビューが繰り返される。
そこだけだと睡魔が襲ってしまうが、時折、かつての作品が差し込まれる。
「キッド」「黄金狂時代」「独裁者」「殺人狂時代」「ライムライト」など。
その瞬間、眠気は吹っ飛び、スクリーンに吸い込まれた。
学生時代、チャップリン作品は相当数観た。
今でも好きな映画人で感動した記憶も鮮明。
当時は半分、ガキだった。
今観たら感じ方は随分と異なるはず。
本作の流れかどうかわからないが、今年はチャップリン作品が上映される。
改めて映画館で観たいと上映中に強く感じた。
本作は前振りだったのか(笑)。
本作の監督は孫のカルメン・チャップリン。
チャップリン家としてその価値を守り続ける必要もあるのだろう。
少しでも協力したい。
映画館でなくとも時間が作れれば過去の作品を一本ずつ観ようと思う。
早いもので今年も残すところあと2日。
2025年はあれやこれやで慌ただしい一年であった。
大学の授業も増え、国際ロータリー第2760地区の次期地区幹事という恐ろしい仕事もやってきて、
自分が何屋さんか分からない年になった。
そんな中でも映画コラムニストとして確実に仕事をこなしたつもり。
今年は映画館で105本、ネット配信で13本、合わせて118本の映画を鑑賞。
日本映画と外国映画はほぼ半分。
これだけの本数を観たのは大学以来。
密かに映画館100本超えを狙っていた。
忙しい、忙しいといいながら本当は忙しくないのでは?
という声も聞こえてくるが、これも大切な仕事。
映画館で100本を観るのは時間調整含めかなり大変。
興味もなくタイミングだけの作品もあるが、それが拾い物だったりと偶然の出会いも大切。
それでは恒例となった2025年のベストテンを発表しよう。
あくまでも主観で根拠はない。
感覚的に選んだ作品なので異論は受け付けない。
誰も文句は言わないか(笑)
■日本映画 2025年ベストテン
1.国宝
2.フロントライン
3.佐藤さんと佐藤さん
4.愚か者の身分
5.宝島
6.でっちあげ 殺人教師と呼ばれた男
7.ふつうの子ども
8.TOKYOタクシー
9.「桐島です」
10.港のひかり
■外国映画 2025年ベストテン
1.サブスタンス
2.愛を耕すひと
3.ワン・バトル・アフター・アナザー
4.Playground 校庭
5.アプレンティス ドナルド・トランプの創り方
6.満ち足りた家族
7.プラハの春
8.リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界
9.TATAMI
10.トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦
日本映画はありきたりな順位になった。
もっとマニアックな作品を選びたかったがほぼ評判通り。
「国宝」は昨日も観て2回目。
半年以上のロングランだが昨日も満席に近かった。
映画ファンとして歴代1位(実写版)の興行収入は嬉しい。
こじんまりとまとまった10本かな。
「敵」「平場の月」「ナイトフラワー」は迷ったが漏れた。
主演女優賞は岸井ゆきの、主演男優賞は綾野剛としておこう。
吉沢亮はきっと他で獲得するし。
一方、外国映画は「ヤバい」作品が並んだ。
まっとうな道から外れた作品が目立つ。
その筆頭格が「サブスタンス」。
これは本当にヤバかった。
「アマチュア」「入国審査」「ラブ・イン・ザ・ビッグシティ」も入れたかったが、残念。
イギリス、デンマーク、アメリカ、ベルギー、韓国、チェコなど幅広く選ぶことができた。
今年は小国の作品が少なかったけどね
来年は今年ほど観れるか心配だが、しっかりとベストテンが報告できるくらいは観たい。
2025年も映画ブログにお付き合い頂き、ありがとうございました。
明日は人気食べ物ブロガーの集大成となりそうです。
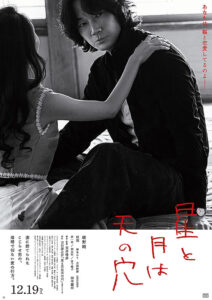
荒井晴彦作品は結構観ている。
近年でも「この国の空」「火口のふたり」は押さえた。
ほぼ男女の恋愛。
それもR18+指定があったりと。
日本映画界では稀有な存在だが、本作も明らかに荒井晴彦的。
当然のようにR18+だし。
一方で吉行淳之介は一作も読んだことがない。
調べてみるとほぼ男女を描く作品ばかり。
純文学といっていいのか。
そんな監督と作家を掛け合わせるとこんな映画になる。
まあ、男と女って所詮こんなものというところ。
いくつになっても男は理屈ばかりでだらしなくあっさりと誘惑に負ける。
巧みな言葉使いで自分をごまかすだけ。
そこも監督と作家の掛け合わせ。
エロ映画も文芸作品に思えてしまうから不思議だ。
本作の舞台は1969年。
映像はモノクロ。
話し方も昭和40年代の映画そのもの。
それが時代を表す。
学園紛争のピークの時期だが、一部の大人は冷めている。
つまらない現実に向き合うことが新たな創造を生む。
時代の分かれ目でもあるのかな。
主役は綾野剛演じる43歳の小説家。
職業柄か、話す一言一言が文学的。
それに絡む女子学生も文学的。
その会話がエロティックな雰囲気を醸し出すが、実際のシーンはそこまででもない。
間違いなく成人映画の領域だが、イヤらしさは感じない。
(映画館は女性客が多かったが、さほど気にならず)
荒井作品は結構ドロドロな男女関係が多いが、本作は意外とあっさり。
ドロドロもドロドロと感じさせない上手さもある。
たわいもない小説家のみだらな生活を描いただけのような気がするが、
人間が本来持つ本性を饒舌に語っている気もする。
分かりやすくいえば、一部の高尚な批評家は絶賛するが、
一般的な批評家は大した評価はしない。
玄人好みの作品といえるのではないか。
本作で一番気になったのは大学生の紀子を演じた咲耶という女優。
初めて知ったが吹越満と広田レオナの娘さん。
いやあ~、大胆な演技。
しおらしい大学生かと思えば、悪女的な妖艶な大人になったり・・・。
綾野剛が振り回されるのも仕方ないか。
荒井晴彦ワールドに浸りたい方はぜひ、観てもらいたい。
年末年始には相応しくないかもしれないけれど(笑)。

アジアの島国に住む僕らにとってヨーロッパの小国を理解するのは簡単じゃない。
報道される表面的なニュースでは実際のお国事情を読み解けない。
高い教養を求められる。
残念ながら僕は持ち合わせていない。
本作はチェコで年間興行収入および動員数1位となる大ヒット作品。
一般的に社会派ドラマが大ヒットすることは少ない。
それも国の暗部を描く作品。
それが大ヒットする背景は国民が思う「プラハの春」が存在したということ。
日本で大ヒットした「国宝」とは異なる感情。
その理由も知ってみたい。
チェコとスロバキアの合作というのも意味があると思うし。
本作を観て思い出したのが映画「存在の耐えられない軽さ」。
もう35年以上前に観た映画なのでほぼ覚えていない。
重かったな・・・と印象くらい。
なぜかそのタイトルだけは未だに思い出す。
偶然かどうか分からないが「存在の~」の主役の名前はトマシュ。
そして本作の主役はトマーシュ。
ほぼ同じ。何かしらの意味があるのか、単に多い名前なのか。
そんなことはどうでもいい。
1968年にチェコスロバキアで起きた事件を実話を基に描くことに意味がある。
それも僕らは知らない、
チェコとスロバキア国民も知らない事実を描くことに意味がある。
それを学べただけでも価値はあった。
当時の社会主義国家がどんな体制で国を統制していたかはなんとなく想像はできる。
本来、言論の自由の代表でもあるマスコミはそれに抗い、
真実を追求することが求められるがどこかの国のように管理下に置かれる。
しかし、数少ない誰かが手を挙げることで賛同者が現れ徐々に意識が変わる。
そうか、本作は1968年を描いているようで、今の時代を描いているのか。
原題である「Vlny」は訳せば「波」。
ここから波を起こそうとしているのか。
と勝手なことを想像したり。
本作は中国やロシアで公開されることはあるのだろうか。
本作を詳しく解説するまではない。
調べて観てもらえばいい。
僕自身は一年を振り返る年末に観ることができたのはとてもありがたい。
映画の持つ力を改めて感じることができた。
チェコやスロバキアの作品に触れ合う機会は少ないが、本作には感謝したい。

東和ピクチャーズさんからオンライン試写会にご招待頂き鑑賞。
このような機会はありがたい。
本作はフランスで2024年年間興行収入ランキング1位となったヒット作。
日本では今週26日から公開される。
自分ではなかなか選ばないジャンルになるので、
むしろ貴重で鑑賞後はとても温かい気持ちになれた。
感謝!
簡単に解説すると、宝石泥棒の親子が障がい者施設のサマーキャンプに紛れ込み、
そこで起きる騒動がいろんな人にある影響を与えていくというストーリー。
ちょっとざっくりすぎるか(笑)。
本作には多くの障がい者役が出演しているが、実際に障がいを持つ方の出演。
それもアマチュアの俳優。
まず彼ら彼女らが素晴らしい。
演技なのか地なのかは分からないが、その行動が泥棒親子を中心にプラスの影響を与えていく。
心はピュアで思うがまま動く姿は本来の人の姿。
僕らは常に周りを意識し、時に忖度し、時に驕り、無理に感情を殺したりもする。
彼らはいつも自然体。
その分、危険が伴ったり、トラブルが起きたりするが、却って人間らしく映る。
そこに巻き込まれた泥棒親子。
最初は逃亡の手段でいいように利用しようとするが徐々に変化し始める。
そのあたりがクスリと笑える。
そして泣けたり。
フランスで興行収入1位になった理由もわかる気がする。
老若男女、誰しもが楽しめる作品といえるだろう。
僕は知らなかったが、主演のアルテュスはフランスで人気のコメディアン。
本作では監督も務めている。
日本でいえば誰に近いかな。
昔だったら志村けんさんのような存在だが、
今のコメディアンに例えると、う~ん、思い当たらない。
役者でいえばムロツヨシみたいな感じかな。
あくまでも雰囲気として・・・。
人気のコメディアンが障がいを持つアマチュア俳優を起用し、
面白おかしく、しかもウルっとくる作品を制作する。
それだけでも話題性はあるのかも。
時々はこんなハートフルコメディを観るのもいい。
ステキな機会をありがとうございました。
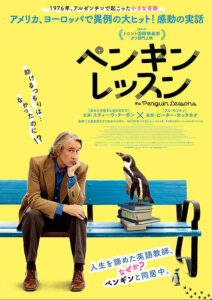
実話をベースにした作品でなければ観ていなかった。
動物もの映画にさほど興味が湧かないのと感動させるのは容易だと思うので・・・。
学生時代、自分たちの主催するイベントに故大島渚監督を招いたことがあった。
ちょうど「南極物語」や「子猫物語」がヒットした時期。
大島監督は「人を感動させようと思ったら、動物を主役にすればいいんだ」
そんなようなことを言われていた。
その影響が残っているかどうか分からないが、これまで動物映画は避けてきた。
本作は実話がベース。
主役に近いペンギンは実際、そんな存在だったのだろう。
やはりズルい。
愛らしいペンギンは多くの人を巻き込み欠かせない存在になっていく・・・。
ついついそちらの方に惹き込まれて、感動的な物語が作られる。
しかし、よかったのはお涙頂戴というわけではなく、
社会背景が混とんとする中で生きる上でのメッセージがみられたこと。
単なる動物映画でない点は評価すべき。
舞台は1976年のアルゼンチン。
心に傷を持つ英語教師トムが赴任した名門学校で繰り広げられる出来事を描く。
サルバトールと名付けられたペンギンは重油まみれの状態をトムに助けられた。
トムは善意というよりはスケベ心から助けたに過ぎない。
上手くいくか行かないかはともかく南米は恋に陥りやすいのかな。
こんな出会いもいいかもね(笑)。
困ったトムはペット禁止の学校内に内緒で持ち帰り・・・。
そんなことでドラマが進む。
僕が動物に関心がないので分からないが、
その存在は人を優しくさせたり、ストレスを発散させたりするのかもしれない。
場合によっては大切な友人ということも。
犬や猫を飼っている知り合いもなくてならない存在のようだし。
だからこそ小さな物語で留まらず、本作のように大きな影響を与える存在になる。
本作は原作通りではないようだ。
社会派ドラマ的な要素が含めれている。
僕は却ってその方がよかった。
本作のタイトルは原題のまま。
まさにThe Penguin Lessons。
多くを教えてくれた。
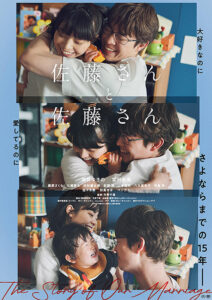
実にイマドキな感じの作品。
天野監督は前作「ミセス・ノイズィ」もそうだが、今を描くのが上手いと思う。
勝手な推測だが天野監督は名大社を知っているはず。
愛知県出身で名古屋大学を卒業しリクルートに5年勤務していた。
ウィキペディアにはそう解説されているので間違いない。
多分・・・。
リクルート時代に磨いた感性が作品作りにも生きているのだろうか。
話が逸れた。
本作は今の時代を象徴している。
「ナイトフラワー」とは違う。
まともな男と女。
自らの目標に向かい日々努力をしている。
マジメで真剣だからこそぶつかり、嫉妬や妬みも生まれる。
両方の佐藤さんの気持ちが理解できるからこそ辛い。
タイトル通り主役は岸井ゆきの演じる佐藤サチさんと宮澤氷魚演じる佐藤タモツさん。
女性目線と男性目線は異なる。
本作が見事なのは両目線に立ち、お互いの感情をはっきりと描いていること。
結婚し子供を持ち仕事をする男女なら納得感は強い。
最近の傾向として女性の方がバリキャリだと男性の劣等感が浮き彫りになる。
お互いに言い分はあり、それもよく分かる。
そしてどちらも悪くない。
そのため平行線を辿ってしまう。
僕がイマドキだと思うのはそんな点。
(自分のことは棚に上げて・・・汗)
なんのことか分からない?
作品を知らない方に簡単に解説。
弁護士を目指し何年も司法試験を受け続けるタモツと
彼を助けるために一緒に勉強し一発で合格したサチ。
サチは弁護士事務所で働き始め、タモツはバイトしながら勉強を続ける。
仮に自分がタモツだとしたら何を感じるか。
「う~ん、大丈夫、大丈夫」と言いながら内心は穏やかじゃない。
それも法律を教えていたサチが一発合格。
タモツは自分が情けなくなるし、サチはむしろ申し訳なく感じる。
映画はそれを間接的に伝える。
普通の男や女はこの状況での言葉は困るはず。
昔のように男が外に出て女が家を守るという構図があれば困ることはないが、
(いや、ベンガルをみるとそうでもない・・・)
いい意味で今はフラット。
耳障りのいいフラットは難題を残す。
これからの時代、幸せなカップルに限ってこんな問題が起きるかもしれない。
時代性でいえば2025年で最も優れた作品ではないだろうか。
最後にひとつ。
今年の主演女優賞は岸井ゆきで決まりかな。
可愛く愛らしい表情、相手を想う切ない表情、感情的に怒る表情、そしてラストシーン。
彼女の演技が映画をワンランク上に押し上げた。
それを感じた作品だった。

ポスターにあるようなシーンはない。
しかし、そのポスターに違和感は感じない。
「なんか、そんな感じがするなあ~」
というのが素直な感想。
ノーテンキに横たわるアロハシャツのオダギリジョーは本作の象徴。
すべてを物語っている。
ほぼ事前情報なしに臨んだ本作。
レビューの点数が高かったので選んだ。
柴咲コウ演じる作家村井理子の存在も初めて知ったし、
自身の体験を綴った作品であるのも初めて知った。
フィクションの要素もあるがほぼ実話。
描かれるのは実の兄の急死が知らされ、葬儀や遺品の処理を行った数日間の出来事。
その兄を演じるのがオダギリジョー。
いい加減でその日暮らしで周りに迷惑を掛けまくるが憎めない存在。
今、気づいたが兄の名前は明かされていない。
お兄ちゃんとかお父さんとか呼ばれるだけ。
それでも十分成り立つ。
そんな兄だが子供のころから要領はよく母親からも愛されていた。
妹の理子は嫉妬し「いなくなればいい」と思いながら大人になった。
唯一の家族であり繋がりは続くが、近くて遠い間柄。
兄を疎ましく思いながらも、兄弟愛はそこそこ。
そしてもう一人。
兄の元妻の満島ひかり演じる加奈子。
「夏の砂の上」ではオダギリジョーと満島ひかりは兄妹だったが、ここでは元夫婦。
他に役者がいないの?
と思ったりもしたが、この関係性は悪くはない。
満島ひかりの母親役はあまりイメージになかったが、本作では抜群。
柴咲コウも妹役をせつなく可愛らしく演じていたが、ここでは満島ひかり。
兄が引き取った息子との会話には思わず涙が出そうになった。
えっ、ネタバレになってないよね。
デキるキャリアウーマンやアバズレな役が多いが、お母さん役も似合うんだ。
改めて演技力にあっぱれ。
これはネタバレじゃないよね。
少しだけバラすと亡くなった兄は理子や加奈子の前に登場する。
それがリアルだとホラー映画だが、あくまでも想像の世界。
その中でもっともらしい会話をする。
それがとても温かく愛を感じさせる。
いい加減でろくでなしの兄が人間味溢れる魅力的な兄になる。
何も変わってはいない。
それが本来の姿だが、表に立つといい加減でろくでなしになってしまう。
そもそも人間なんてそんなものかもしれない。
観終わった後とても爽やかで優しい気持ちになれる映画。
やっぱ、家族も兄弟も大切だしね。

「人生の悲劇は二つしかない。
一つは、金の無い悲劇。
そして、もう一つは、金のある悲劇。
世の中は金だ。金が悲劇を生む。」
これはNHKドラマ「ハゲタカ」で使われた名言。
シチュエーションは異なるが、この言葉がしっくりとくるのが本作。
映画を観終わった後に思った。
この秋は見応えのある日本映画が続く。
しかし、重くて暗い作品が多すぎないか。
「愚か者の身分」「盤上の向日葵」「爆弾」「港のひかり」
この2ヶ月だけでもそんな作品が並ぶ。
その中でも本作はさらに重くて暗い。
北川景子の美しさがなければ辛くて観れなかった。
それは大袈裟だが、非現実的でありながら現実的な世界。
シングルマザーで近い生活はあるのかもしれない。
何を大切にするか、何を護るか。
シングルマザーの中には育児放棄や虐待を行う者もいる。
一方で愛情を注ぎながらも先が見えず苦しむ者もいる。
少なくとも愛情を注ぐ母親には何とかなって欲しいと思うが、
世間は上辺でしか物事を判断できない。
それが不幸を加速させる。
そんな場所に北川景子演じる夏希は存在する。
彼女がドラックの売人になることに「やめておけ!」と心の中で叫んでも、
どこか同情し許してしまう。
夏希と偶然出会った女性格闘家の多摩恵は自分と重ね合わせながら、
夏希とその家族と守っていく。
多摩恵を演じるのは森田望智だが格闘能力もなかなかなもの。
この2人を中心にドラマはあらぬ方向に向かっていく。
まあ、ストーリーはそんなところまでにしておこう。
そして、冒頭の金のない悲劇と金のある悲劇。
夏希の家族と多摩恵は一体どうなっていくのか。
明るい未来を想像する人は少ない。
いや、いないと思う。
夏希と多摩恵はどうか。
望みがある限り前に進む。
諦めない。
それが正しい姿。
僕は本作のラストは内田監督の優しさだと感じた。
希望は持ち続けるのだと。
本作にはもう一人母親が登場する。
裕福な家庭でありながら幸せを感じない田中麗奈演じるみゆき。
娘との繋がりは金。
後妻とも本妻とも判断がつかない。
彼女も最大の愛情表現を示す。
それはゆがんだ愛情表現。
貧困でありながら真っすぐな愛情。
裕福でありながらゆがんだ愛情。
皮肉を感じる。
世の中は金だ。金が悲劇を生む。
そんな作品だった。